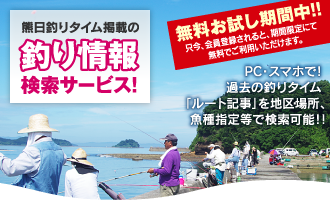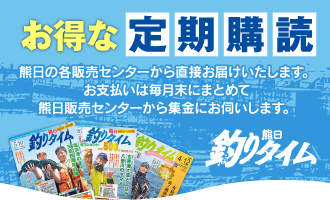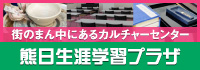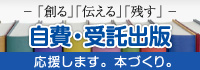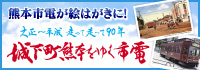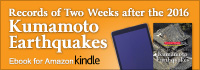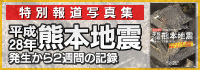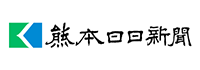あ行
- あおしお(青潮)
- 酸素濃度が下がった低層水が水面まで上昇する現象。海が青白色や緑色に見え、魚介類は酸欠で死ぬこともある。
- あおもの(青物)
- アジ、サバ、ヒラマサ、カンパチなどの背が青い、中層を泳ぐ回遊魚。
- あおる
- まき餌カゴなどに入れた餌をまくために竿を上下に振ること。「しゃくる」とも言う。
- あかしお(赤潮)
- プランクトンの大量発生で潮が赤く濁る現象。海中は酸欠状態になって魚介類が死ぬことも多い。
- アクション
- ロッド(竿)の操作や、ルアー(擬似餌)の動きのこと。
- あげしお(上げ潮)
- 潮が満ちてくる状態。「上げ」とも言う。
- あげっぱな(上げっ端)
- 最干潮からの満ち始めのことで、潮が動くので魚の活性が高くなり、よく釣れる。
- あさば(浅場)
- 水深の浅い所。
- あさまずめ(朝まずめ)
- 日の出前後の時間帯。魚が餌を求めて活発に動くため、釣りによい時間帯。
- あしでつる(足で釣る)
- ルアー釣りや渓流釣りなどで移動しながらポイントを探る釣り方。
- アタック
- ルアーに魚が飛び掛かること。
- あたり(当たり)
- 魚が針(フック)に食いつき、竿やウキ、道糸(ライン)に反応が現れる状態。
- あたりじお(当たり潮)
- 釣り座の正面にぶつかるように流れくる潮。
- あなづり(穴釣り)
- テトラや石積み、岩場のすき間に仕掛けを入れて釣る方法。
- あなば(穴場)
- 自分だけが知っている好釣り場。
- アミ
- アミエビのことで、サビキ釣りに使われる。
- あらぐい(荒食い)
- 産卵前や時化(しけ)後などに魚の食欲が高まり、むさぼり食べること。
- あわせ(合わせ)
- 当たりがあった瞬間、竿を上げたり、引くなどして魚の口に針をかけること。
- あわせぎれ(合わせ切れ)
- 合わせが強すぎたり、魚が大きすぎて、道糸やハリスが切れること。
- アンカー
- いかり(錨)のこと。
- アングラ―
- 釣り人のこと。
- イカスッテ
- イカ釣りの際に使う疑似餌。
- いきえ(生き餌)
- 生きている小アジや小イワシなど。スズキやブリ、ヒラメなどの泳がせ釣りで使われる。
- いぐい(居食い)
- 魚が居ながらにして餌を食う状態で、当たりが明確に出ない。
- いけじめ(生け締め)
- 魚の鮮度を保つため、急所をナイフなどで刺して殺すこと。活(け)〆も同じ。
- いしごかい(石ゴカイ)
- キスゴ虫とも呼ばれる赤みを帯びた小さい虫。キスやハゼのような小魚、クロ釣りなどに使われる。
- いしづき(石突き)
- イシダイ竿やタマン竿などの一番下にある、竿尻を保護するパーツ。
- いしもの(石物)
- 磯のイシダイ、イシガキダイなどを指す。
- いっか(一荷)
- 2本の針に同時に魚が掛かること。「ダブル」ともいう。
- いつき(居付き)
- 季節による移動や回遊をしない魚。
- いっそく(一束)
- 魚の数え方で、100匹のこと。ハゼやキスなどの数釣りで使う。
- いっぱい
- 満潮のこと。
- いとふけ(糸ふけ)
- 風や潮の流れなどにより、道糸がたるむ状態で、釣果が落ちる。
- いれがかり(入れ掛かり)
- アユ釣りで、おとりを泳がせるたびに掛かる状態。
- いれぐい(入れ食い)
- 仕掛けを投入するたびに魚が釣れる状態。
- ウェーダー
- 立ちこみ釣りや渓流釣りなどで使われる、胴や胸まである長靴。
- うかせる(浮かせる)
- 掛けた魚を取り込む際、頭を水面に出し、空気を吸わせておとなしくさせること。
- うがん(右岸)
- 川の下流に向かって右側。
- うきさんばし(浮き桟橋)
- 水に浮く素材で作った箱型の桟橋。干満の差が大きい港に設置される。
- うきした(浮子下)
- ウキから針までの長さ。
- うげん(右舷)
- 船首に向かって右側。
- うちこみ(打ち込み)
- 狙ったポイントに仕掛けや餌を連続投入すること。
- うねり
- 遠方で発生した台風の影響を受けて伝わってくる起伏が大きい波。
- うわじお(上潮)
- 海面近くの表層流。
- うわばり(上針)
- 複数の針がついている仕掛けの上の針。
- うわもの(上物)
- 主に海の表層から中層にいる魚。特に磯釣りではクロやチヌなどを指し、イシダイなどの「底物」と区別している。
- エギ(餌木)
- ミズイカ(アオリイカ)を釣るための和製ルアー(疑似餌)。
- エギンガ―
- エギングをするアングラー(釣り人)。
- えさとり(餌取り)
- 餌だけを取っていく小魚。ヘラブナ釣りでは「ジャミ」と呼んでいる。
- えだす(枝素)
- 幹糸から枝状に出た針。
- えらあらい(鰓洗い)
- スズキなどが海面で首を振って針を外そうと暴れること。
- えんとう(遠投)
- 遠くのポイントに仕掛けを投げること。
- おいぐい(追い食い)
- サビキ釣りなどで残りの針に魚が続けて掛かること。
- おおしお(大潮)
- 満月と新月の前後に起きる、干潮と満潮の潮位の差が最も大きい潮回り。
- おおども(大艫)
- 船の最後部。
- おかづり(陸釣り)
- 陸地から釣ることで、「おかっぱり」とも言う。
- おきあがり(沖上がり)
- 沖での釣りが終わり、帰港の途に就くこと。
- おきいそ(沖磯)
- 陸地から離れた磯。
- オキアミ
- 南極オキアミのことで、付け餌、まき餌ともに使われる定番の餌。
- おきざお(置き竿)
- 竿を手に持たないで防波堤や竿掛けなどに置いたまま当たりを待つ釣り方。
- おきづり(沖釣り)
- 船釣りのこと。
- おさえこみ(押さえ込み)
- 掛かった魚が穂先をじわりと引き込む当たり。「もたれる」とも言う。
- おくりこむ(送り込む)
- 当たりがあったとき、しっかりと食い込ませるため、道糸をリールから少しずつ出すこと。
- おち(落ち)
- 魚が越冬や産卵のために深場へ移動すること。またアユなどが川を下ること。
- おちこみ(落ち込み)
- 水深が急に深くなった地形。
- おとしこみ(落とし込み)
- 防波堤の際やケーソンの際などに沿って、仕掛けをゆっくりと沈めて釣る方法。
- おまつり
- 自分の仕掛けと他人の仕掛けが絡むこと。
- おもかじ(面舵)
- 船の進行方向に向かって右にかじをきること。
- オモリ(重り)
- 仕掛けを沈めるためのもの。「シズ」とも言う。
- おもりふか(重り負荷)
- 竿やウキに適したオモリの号数(許容数値)。
- およがせづり(泳がせ釣り)
- 小アジや小イワシなどの生き餌を針にかけて、泳がせながら大型の魚を狙う釣り。「のませ釣り」とも言う。
- オルブライトノット
- 細いライン(道糸)と太いラインとをつなげる結び方。
か行
- ガイド
- 竿につけられた道糸を通すための環状のもの。
- かいゆうぎょ(回遊魚)
- 産卵場所や餌を求めて広い海域を回遊する魚。
- カウントダウン
- キャストしたルアーを、数えながら沈ませていくこと。水深やタナを探ることができる。
- かえし(返し)
- 針がはずれにくいようにする、針先の鋭い突起(バーブ)。かえしがないものがスレ針。
- かくれね(隠れ根)
- 海面の下の方に隠れている岩礁。
- かけあがり(駆け上がり)
- 海底が深場から浅場に向かって坂のようになっている所で、魚が集まりよく釣れる。
- かごつり(カゴ釣り)
- 寄せ餌をナイロンカゴや反転カゴなど専用のカゴに詰め、遠投して釣る方法。
- かしばらい(河岸払い)
- 船が岸から離れること(出船)。
- かた(型)
- 魚の大きさ。
- かたげん(片舷)
- 船、ボートの右舷、左舷のどちらか一方。
- かたじくリール(片軸リール)
- スプールを固定する軸が片方で固定されており、ライン操作が比較的楽に行える。
- かたてんびん(片てんびん)
- 仕掛けが絡まないように片方に長く伸びている金具。
- かみつぶし(噛み潰し)
- 小さなオモリで中央に切り込みがあり、その中に道糸やハリスをはさんで固定する。割りビシとも言う。
- からあわせ(空合わせ)
- 当たりと勘違いして竿を上げて合わせること。
- がんだま(ガン玉)
- 小さな鉛のオモリ。
- かんぬき(閂)
- 魚の口の合わせ目。
- かんのんづり(観音釣り)
- 狭い場所や流れのある場所で、釣り人が横一線に並び、順繰りに入れ替わりながら釣るやり方。
- ききあわせ(聞き合わせ)
- 魚が掛かっているかどうか、ゆっくり竿を立てるなどして合わせてみること。
- きく(聞く)
- 魚が餌を食べているかを確かめるため、道糸を張って様子を見ること。
- ぎじえ(疑似餌)
- 餌となる昆虫、小動物、小魚などに似せて作った人工餌。ルアー、毛針、フライ、餌木などがある。
- きすいいき(汽水域)
- 河口など淡水と海水とが混じりあう水域。
- キャスティング
- 仕掛けやルアーを投げること。
- キャッチ&リリース
- 釣った魚を持ち帰らず、その場で放流すること。
- キャビン
- 船の客室をいい、釣り船は釣り人が休む場所。
- ギャフ
- 釣った魚を取り込む手鈎(かぎ)。
- ぎょえい(魚影)
- 魚の数のことで、多ければ「魚影が濃い」、少なければ「魚影が薄い」と言う。
- きわ(際)
- 防波堤や岸壁、岩礁の端のこと。
- くい(食い)
- 魚が餌を食べること。
- くいあげ(食い上げ)
- 魚が餌を食べた際、底に向かわず、上に向けて泳ぐこと。ウキが倒れたり、仕掛けがフッと軽くなるなどする。
- くいがたつ(食いが立つ)
- 魚が餌をよく食べ、ウキに反応が頻繁に現れ、よく釣れ始めること。
- くいこみ(食い込み)
- 魚が餌やルアーなどを食い込む状態。
- くいしぶり(食い渋り)
- 魚の活性が下がりあまり餌を食べなくなること。
- クーラー
- 釣った魚の鮮度を保つためのアイスボックス。
- くちをつかう(口を使う)
- 魚が餌を食べること。
- くちぎれ(口切れ)
- 針が口からはずれてしまうこと。
- クッションゴム
- 魚の急激な引きの衝撃を和らげるもの。
- けいこうライン(蛍光ライン)
- 道糸の状態を見るための蛍光色の糸。
- ケーソン
- コンクリ―ト製の箱型や円筒形の波止。
- けしこむ(消し込む)
- 魚が掛かって、ウキが水中に沈む状態。
- げどう(外道)
- 自分が釣ろうとする本命以外の魚。言葉の響きがよくないため、「他魚」と言いかえることが多い。
- ごう(号)
- 主に糸やオモリのサイズを表す単位。
- こしお(小潮)
- 干潮と満潮の潮位の差が少ない潮回り。
- こづく(小突く)
- 竿をあおってオモリを上下させ、海底をたたき砂煙を上げて魚を寄せること。
- こっぱ(木っ端)
- 取るに足らない小さな魚のこと。
- こませ
- 魚を寄せるためのまき餌のこと。
- ごもくづり(五目釣り)
- いろいろな魚を釣ること。
- こもの(小物)
- 小さい魚のこと。
- ごろたいし(ゴロタ石)
- 丸い中小の石。たくさんある所がゴロタ場。
- こんいんしょく(婚姻色)
- 繁殖期の間、一時的に体の色が変わることで、海のアイナメやマダイ、川ではオイカワ(シラハエ)などが知られる。
さ行
- さおあげ(竿上げ)
- 船釣りでポイントを移動する際、いったん仕掛けを上げること。
- さおいっぽん(竿1本)
- 磯竿(約5・3m)の長さを目安に、ポイントまでの距離やタナの深さなどを表す。
- さおがしら(竿頭)
- 遊漁船などで、狙いの魚を一番多く釣り上げた人。
- さおさき(竿先)
- 穂先(竿の先端部)。
- さおした(竿下)
- 竿の真下か、竿が届くごく近い範囲。
- さおじり(竿尻)
- 竿の手元側の一番端。
- さかしお(逆潮)
- 風向きと反対に流れる潮のこと。
- さきいと(先糸)
- 道糸の先に付ける糸のこと。アユやヤマメ釣りなどで使う天井糸に同じ。
- さきちょうし(先調子)
- 竿先が柔らかく、繊細な当たりがとりやすいもの。
- さぐる(探る)
- 魚のいるところを探すこと。
- さげしお(下げ潮)
- 潮が引いていく状態。「下げ」ともいう。
- さげどまり(下げ止まり)
- 最干潮のこと。
- ささにごり(ささ濁り)
- 水がやや濁っている状態。
- さしえ(刺し餌)
- 付け餌のこと。
- さそい(誘い)
- 仕掛けを動かして魚の興味を引き、餌に食いつくようにすること。
- さそいあげ(誘い上げ)
- 魚の食い気を誘うため、ゆっくりと仕掛けを上げること。
- サビキ
- 魚皮やゴム、ビニールなどを針に巻いた疑似針を何本も付けた仕掛け。
- さびく
- 追い食いさせるため、仕掛けを少しずつ引くこと。
- サミング
- リールのスプールを指で押さえ、道糸の出るスピードや量を調節すること。
- さらし(晒し)
- 磯に打ち寄せる波が白く泡立ち、払い出している状態。クロ釣りのポイント。
- サルカン
- 道糸とハリスをつなぎ、糸がよれないようにするもの。ヨリモドシとも言う。
- じあい(時合)
- 魚が餌に食いつく時間帯。
- じいそ(地磯)
- 沖磯に対して、陸続きの磯を指す。
- シーバス
- スズキのこと。
- シェイキング
- ロッドを細かく振動させ、ルアーに動きを与えること。
- しおうら(潮裏)
- 潮が当たらない所。
- しおおもて(潮表)
- 沖からの潮が当たる所。
- しおがわり(潮変わり)
- 潮の干満が変わること。
- しおだるみ(潮だるみ)
- 潮の流れが止まるか、止まる寸前の状態。
- しおどおし(潮通し)
- 潮の流れがよいこと。
- しおどまり(潮止まり)
- 干満の変わり目で、潮の流れが止まった状態。
- しおまち(潮待ち)
- 釣りによい潮の具合を待つこと。
- しおまわり(潮回り)
- 潮汐のことで、大潮、中潮、小潮、長潮、若潮がある。
- しおめ(潮目)
- 潮流がぶつかる場所にできる境目。
- しかけ(仕掛け)
- 魚を釣るための道糸やハリス、オモリ、針などでできた部分。
- じかた(地方)
- 陸寄りのこと。
- ジギング
- ジグと呼ばれるルアーを使う釣り方の一つ。
- しけ(時化)
- 悪天候のために海が荒れること。
- しずみせ(沈み瀬)
- 潮が引いても現れない岩礁。
- しちさんちょうし(七三調子)
- 竿の長さを10等分にして、竿尻から7、穂先から3の割合で曲がる調子。
- しぶしぶ(渋々)
- ウキが海面すれすれの状態になること。
- しめこみ(締め込み)
- 魚の引きが強く、竿を海面に引き込むこと。
- しめる(締める)
- 魚をおいしく食べるため、急所を刺して死なせること。血抜きも合わせてする。
- ジャーク
- ロッドを大きくしゃくってジグ(疑似餌)を垂直方向に大きく泳がせること。
- しゃくる
- 竿を上下させ、仕掛けを躍らせる動作。「あおる」とも言う。
- じゃみ
- 餌取りの小魚。ヘラブナ釣りで使われる言葉。
- しゅっせうお(出世魚)
- 成長とともに呼び名がかわっていく魚。ブリ、ボラ、スズキなどがいる。
- シンキング
- 沈むタイプのルアー(プラグタイプ)。
- シングルフック
- 一本針のこと。トリプルフックは三本針。
- しんこ(新子)
- 幼魚のこと。
- じんこうえさ(人工餌)
- 魚が好む臭いや材料で人工的に作った餌。
- じんこうぎょしょう(人工漁礁)
- 魚を集めるため、海底に設置された構造物。
- すいちゅううき(水中ウキ)
- 水面付近と流れが違う場合に使われるウキ。浮力を抑えているので沈み、潮流に乗る。
- スイベル
- ヨリモドシのこと。簡単に糸と糸をつなぐ小物。
- スカリ
- 網状の魚入れ。
- スキンサビキ
- 針に薄いゴム(スキン)を付けた仕掛け。
- ステイ
- ルアーの動きを一時的に止めることで、魚に食う時間を与える。
- すていし(捨て石)
- 波止や護岸など、基礎部分に敷き詰められた岩やブロック。
- すていと(捨て糸)
- 根掛かりしたときに切れ、被害をオモリの部分だけにとどめる糸。
- すておもり(捨てオモリ)
- 細い糸でオモリを結び、根掛かりしたときにオモリだけ切り離せるようにした仕掛け。
- ストップアンドゴー
- ルアーを引いたり、止めたりして弱った魚を演出するテクニック。
- ストラクチャー
- 魚が隠れやすい水中の障害物。
- ストリンガー
- 釣った魚を生かしてつないでおく用具。
- すなずり(砂ずり)
- 投げ釣り仕掛けの幹糸を補強するために二重によった部分のこと。
- すばり(素針)
- 当たりがとれずに空振りすること。
- スピニングリール
- 投げ釣りやルアーフィッシングなどに使用されるリール。
- ずぼづり(ズボ釣り)
- 竿下の海底から中層をてんびん仕掛けなどで釣る方法。
- スレ
- 針が口以外の場所に刺さって釣れること。
- スレ針
- 針の内側に返しのない針。
- スパンカー
- 船の船尾に付ける帆のことで、風見鶏のような働きをする。船首を常に風上に向けられる。
- スローリトリーブ
- ルアーをゆっくり引くこと。シーバスやメバル釣りの基本。
- せ(瀬)
- 川で流れが速い浅い場所。海では沖磯。
- せがけ(背掛け)
- 生き餌の魚の背中に針を掛けること。
- せじり(瀬尻)
- 瀬の終わる所。
- せわたし(瀬渡し)
- 沖の防波堤や磯に渡す専門の船。
- せんどうがかり(船頭掛かり)
- 船頭が世話をしてくれる釣り。
- ぜんゆうどう(全遊動)
- ウキ釣りで、道糸にウキ止めをつけずに、仕掛けを落とし込んでいく釣り方。
- そこあれ(底荒れ)
- 海が時化などで荒れ、海底の砂泥などが舞い上がった状態。
- そこしお(底潮)
- 海の底層の潮流。
- そこだち(底だち)
- 仕掛けが海底に到達すること。
- そこづり(底釣り)
- 海底に餌をつけて釣ること。
- そこをきる(底を切る)
- オモリを底から離すこと。
- ソフトルアー
- 自然に分解される軟らかい素材などでできたグラブやワームなどのルアー。
た行
- ターゲット
- 狙いの魚。
- たかぎれ(高切れ)
- 道糸が途中で切れること。
- たち(立ち)
- 水深のこと。水面からタナまでの深さも言う。
- タックル
- 釣り道具のこと。
- タナ(棚)
- 魚の遊泳層。
- タナとり(棚取り)
- タナに仕掛けを合わせること。
- たまあみ(玉網)
- 魚をすくう網。タモともいう。
- ためる
- 魚の強い引きに竿を立て、竿の弾性を生かして耐えること。
- たんざお(短竿)
- 比較的短い竿のこと。
- ちからいと(力糸)
- 投げ釣りで、投げたショックで道糸が切れないようにオモリと道糸の間につなぐ糸。
- チチワ
- 道糸、ハリスなどを結ぶための、糸の先端の輪。
- ちもと(針元)
- 針の糸を結ぶ部分。
- ちょうか(釣果)
- 釣った魚の量や大きさなどの成果。
- ちょうこう(釣行)
- 釣りに行くこと。
- ちょうし(調子)
- 竿の曲がり具合のことで、竿先が曲がるものを先調子、真ん中付近が曲がるものを胴調子という。
- ちょうしゅ(釣趣)
- 釣りの味わい。
- ちょうせき(潮汐)
- 潮が周期的に満ち引きをすること。
- ちょんがけ(ちょん掛け)
- 針先にちょっと餌を付けること。
- つけえ(付け餌)
- 針に付ける餌。
- つぬけ(つ抜け)
- 10匹以上釣ること。ひとつからここのつまでは「つ」があるが、10からはなくなるので言う。
- ツノ
- イカ釣りの際に使う道具。スッテやプラヅノがある。
- つりざ(釣り座)
- 釣りをする場所のこと。
- てかえし(手返し)
- 餌付け、仕掛けの投入の作業を繰り返すこと。
- テグス(天蚕糸)
- 釣り糸のこと。
- ティップラン
- エギを沈めずに一定層を水平に探る釣り方。
- テトラポット
- 消波ブロックのこと。
- テンション
- 糸にかかる力。
- てんびん(天秤)
- 仕掛けを投げたときに糸が絡むのを防ぐ道具。
- テンヤ
- オモリと針が一体化した道具。
- トゥイッチング
- ロッドを上下左右に小刻みに動かし、ルアーに不規則なアクションをつけること。
- とうさい(当歳)
- その年に生まれた魚のことで、デキともいう。
- どうつきしかけ(胴突き仕掛け)
- 一番下にオモリをつけて、その上に枝針が数本ついている。
- どうのま(胴の間)
- 人体の胴になぞらえて、船の中央部をいう。
- としなし(年なし)
- 生まれてから何年経ったか不明な魚。チヌ(クロダイ)なら、50㎝以上のものを指すことが多い。
- とばしうき(飛ばしウキ)
- 仕掛けをより遠くに飛ばすためのウキ。
- とも(艫)
- 船尾(船の後方部)。
- ドラグ
- 魚の強烈な引きによる糸切れを防ぐため、道糸の出し入れを調節する機構。
- とりかじ(取り舵)
- 船の進行方向に向かって左にかじをきること。
- とりこみ(取り込み)
- 掛かった魚をタモ(玉網)やギャフ(手かぎ)などで上げること。
- とりやま(鳥山)
- 海面近くにいる魚を狙って海鳥が群れている場所。
- トレブルフック
- ルアー用の3本イカリ針のこと。
な行
- ながざお(長竿)
- 長い竿。
- なかしお(中潮)
- 大潮と小潮の間の潮のこと。中潮の2日目はよく釣れるとも言われる。
- ながしお(長潮)
- 小潮回りの最終の潮で、干満の差が最も小さく、釣果はあまり期待できない。
- なかだるみ(中だるみ)
- 一時的に当たりがなくなること。
- なぎ(凪)
- 風も、波もない穏やかな海の状態。
- なだ(灘)
- 沖合の波が荒く、潮流が速い海域。
- ナブラ
- 魚の群れ。
- なみつぎ(並継ぎ)
- 竿の継ぎ目が差し込み式になっているもの。
- にまいじお(二枚潮)
- 海の表層と低層で潮の流れが違うこと。糸ふけが出て、当たりが取りづらくなる。
- ぬいざし(縫い刺し)
- 針に餌を縫うように2~3回刺すこと。
- ぬきあげ(抜き上げ)
- 針に掛かった魚をそのまま竿で一気に上げてしまうこと。「ぶり上げる」とも言う。
- ね(根)
- 海底や川底にある岩礁。
- ネイティブ
- 天然魚のこと。
- ねがかり(根掛かり)
- 仕掛けが海底の障害物に引っ掛かること。
- ねざかな(根魚)
- 岩礁の多い所をすみかにしている魚で、アコウ、カサゴ、メバル、アイナメなどがいる。
- ねずれ(根ずれ)
- 海底の岩に道糸やハリスがこすれて傷つくこと。
- ねむりばり(ねむり針)
- 針が内側に曲げられた針で、根掛かりせず、魚の掛かりがいいとされる。
- のうかん(納竿)
- 釣り終えて、釣り具を片付けること。
- のされる
- 魚の勢いが強く、竿を水平方向に持っていかれるような状態。水平に近くなるほど、仕掛けが切れる可能性が高まる。
- のじめ(野締め)
- 魚のうまみを保つため、釣り場で魚を殺すこと。
- のっこみ(乗っ込み)
- 産卵のために魚が浅場に群れる状態。
- のべざお(延べ竿)
- リールを必要としない竿のこと。
- のる(乗る)
- 魚やイカ、タコが針に掛かること。
は行
- ばあれ(場荒れ)
- ポイントに大勢の人が釣りに来て、釣り場が荒れてしまうこと。
- はいごうえさ(配合餌)
- まき餌を目的に、何種類かの材料をブレンドした餌。
- ばくちよう(爆釣)
- ものすごく釣れること。
- バース
- 船を係留する場所。
- はえね(はえ根)
- 磯から沖に張り出している岩礁。
- ばけ(化け)
- 魚の皮などで作った擬似餌。
- はしる(走る)
- 掛かった魚が逃げようとして泳ぎ出す状態。
- はちのじびき(8の字引き)
- ルアーを引くテクニックで、足で「8」の字を描くように操作すること。
- バッククラッシュ
- 仕掛け投入時や合わせる際、リールのスプールが回りすぎて、余分に糸が出て絡むこと。
- ハナ(端)
- 岬や島などの突き出た先端部。「●●島のハナ」などと言う。
- はながけ(鼻掛け)
- 魚の鼻に針を通して、生き餌にすること。
- ハネ
- 魚が水面で跳ねること。
- はやあわせ(早合わせ)
- 当たりに素早く合わせること。
- パヤオ
- 浮き漁礁。
- パラシュート
- 船の流し釣りで使うパラシュート型のアンカーのことで、「シーアンカー」とも言う。潮流と水の抵抗を利用してボートを流す。
- ばらす
- 針に掛かった魚を逃がしてしまうこと。
- ハリス(針素)
- 道糸とつなぎ、針を結ぶ糸。
- ばんのうざお(万能竿)
- 魚の種類に合わせなくても使える竿。
- ビク(魚籠)
- フラシともいい、釣った魚を入れる道具。
- ビシ
- オモリのこと。底にオモリが付いたコマセカゴを指すことも。
- ヒット
- 魚が掛かること。
- ひれをうつ(ひれを打つ)
- 抵抗していた魚が弱った様子。
- ヒロ(尋)
- 両手をいっぱい広げたときの間隔(1ヒロは約1.5m)。磯釣りはウキ下の長さ、船釣りでは深さを表すのに使う。
- ファストリトリーブ
- ルアーを速いスピードで引くこと。
- フィッシュイーター
- 小魚などを捕食する魚。
- ふかせづり(ふかせ釣り)
- オモリを打たずに自然に仕掛けを漂わせる釣り方。
- ふかば(深場)
- 水深がある釣り場。
- ふさがけ(房掛け)
- 針に虫餌を何匹もぶら下げる餌の付け方。
- フッキング
- フック(針)が魚の口に掛かる状態。
- ぶっこみ(ぶっ込み)
- オモリと針のみの仕掛けで近い範囲を探る釣り方。
- プラグ
- ミノータイプのルアー。
- ブラクリ仕掛け
- 根魚釣りなどでよく使われる仕掛けで、オモリの下に針がくくってある仕掛け。
- フラッシャー
- 光沢のあるビニールのような素材のことで、サビキ仕掛けに使用する。
- フリーフォール
- ハマチなどを狙うメタルジグを自然に沈めること。
- ふりこむ(振り込む)
- 仕掛けを投入すること。
- フローティングミノー
- 海面に浮かぶタイプのルアー。
- フロロカーボン
- ハリスなどに用いられ、ナイロン糸より伸びが少ないので魚の当たりがよく分かる。
- ベイト
- 餌となる小魚。
- へさき(舳先)
- 船首(船の前方部)。
- べたなぎ(べた凪)
- 風も波もない穏かな海の状態。
- へち(端)
- 堤防や護岸のすぐ際。「辺」とも。
- ボイル
- 大型の魚が餌となる小魚を海面まで追い詰め、海面が沸き立っている状態。
- ポイント
- 魚がよく釣れる場所のこと。
- ぼうず
- 魚が1匹も釣れない状態。
- ぼうびき(棒引き)
- 深場の岸を探るとき、ルアーにアクションをつけずにひたすら糸を巻くこと。
- ほさき(穂先)
- 竿の先端で一番細い部分。
- ポッパー
- 水面を走り、水しぶきと音で食性を刺激させるルアー。
- ボトム
- 海底、水底のこと。
- ポンピング
- 魚を引き寄せる時に使うテクニックで、竿を上げ、下げるときに糸を巻く動作。
ま行
- まきえ(撒き餌)
- 魚を寄せるためにまく餌。寄せ餌、こませとも言う。
- まごばり(孫針)
- 2本針の仕掛けで補助的な針。
- まずめ
- 日の出、日没前後の魚がよく釣れる時間帯のことで、「朝まずめ」「夕まずめ」という。
- みおすじ(澪筋)
- 船の通れる海溝。
- みきいと(幹糸)
- 胴突き仕掛けで、枝針を突けるときのハリスを結ぶ太い糸。
- みぞ(溝)
- 海底が一段と落ち込んだ所。
- みちいと(道糸)
- 竿と仕掛けを結ぶ糸、リールに巻く糸でもある。
- ミノー
- 小さな魚を形どったルアー。
- みゃくづり(脈釣り)
- ウキを使わずに脈を計るように当たりだけで釣る方法。
- みよし(舳)
- 船の先端部(船首)。
- むこうあわせ(向こう合わせ)
- 魚が自ら食いついて針掛かりしてしまう状態。
- もあな(藻穴)
- 藻と藻との切れ目。
- もたれ
- 魚が餌に食いついたとき、竿の穂先に伝わる、わずかな重み。
- もやいづな(舫い綱)
- 船と船、船と陸を結ぶ船のロープ。
や行
- やびき(矢引き)
- 弓を矢で射るときに広げる両手の幅。1ヒロの約半分(約75㎝)。
- やまだて(山立て)
- 山や岬など陸地の目標物を目印に操船して漁場に到達すること。
- やりとり(やり取り)
- 針掛かりした魚をあしらいつつ手元に寄せる動作。
- ゆうぎょせん(遊漁船)
- 利用客を漁場に案内し、釣りをさせる船。船釣り、瀬渡し、防波堤渡し、イカダ渡しなどを行う。
- よせえ(寄せ餌)
- 魚を寄せるための餌。
- ヨブ
- 潮の流れによって出きる砂底の起伏したところ。
ら行
- ライズ
- 大型の魚が餌の小魚を追って水面で反転すること。
- ライトタックル
- 軟らかいロッドに、小型のリール、細いラインを組み合わせたもので、大型の魚を狙うゲーム性が高い釣りを楽しめる。
- ライン
- 道糸。
- ランディング
- 魚を取り込むこと。
- リーリング
- リールで糸を巻く動作。
- リール
- 道糸を巻き取る道具。
- リトリーブ
- ルアーを引いてくること。
- りょうじくリール(両軸リール)
- スプールを固定する軸が両方で固定されており、大物に対して威力を発揮する。
- リリース
- 釣った魚を放流すること。
- ルアー
- 疑似餌のことで、スプーン、スピナー、プラグ、ジグなど、釣り方に合わせて多種多様なタイプがある。
- ロックフィッシュ
- 根魚のこと。
- ロッド
- 釣り竿のこと。
わ行
- ワーム
- 柔らかいルアーで、ミミズなど虫類の動きをする疑似餌。
- わかしお(若潮)
- 潮が若返る意味があり、これから干満の差が大きくなっていく。
- わりびし(割りビシ)
- 道糸やハリスに、はさめるように切り目が入れてある楕円形のオモリ。
- ワンド(湾処)
- 小さな入り江。